神奈川県高等学校教科研究会
社会科部会公民科会活動報告(社会科部報第93号より)
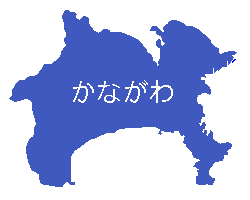
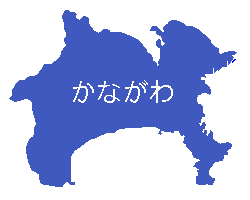
| 公民活動報告(社会科部会報第93号より、2024年10月23日発行) |
| 公民科分科会は年度の前半には独自の企画を行っていない。しかし東京などで開催される様々な研究発表会に参加している。 今回はそれらの研究会から8月19日に慶應大学三田キャンパスで行われた「先生のための夏休み経済教室(高校)」を紹介したい。 この会を主催しているのは「経済教育ネットワーク」という大学教員と高校の教員から構成される任意団体である。同志社大学名誉教授の篠原総一先生を核として,高校の経済教育に問題点を感じている先生方が,日頃から研究や実践発表を行っている。 午前中は金融教育をテーマに外部機関との連携に関する発表が行われた。今回は東京都立農業高等学校で公民科を担当される塙枝里子先生,筑波大学附属駒場中学校・高等学校で家庭科を担当する植村徹先生の発表をもとに,様々な外部機関の活用法や,家庭科と社会科との連携に関する発表が行われた。 次に日本大学経済学部教授の安藤至大先生から労働を通じて学ぶ経済教育に関するお話があった。「経済を学ぶ≠経済学を学ぶ」ではないが,経済学は社会を見る上では優れたレンズであると語られ,経済学の各分野が扱う内容を宝島の地図のように表示するわかりやすい内容であった。 午後は「人ロオーナス時代の日本社会のゆくえを読み解く」と題して京都大学大学院経済学研究科・経済学部教授の諸富徹先生の講演があった。経済不振を人口要因から単純に説明するのではなく,社会のシステムが少子化に対応していないことに求める論調はたいへん参考になった。世界的な資源・食糧問題では人口増加が問題だと教えながらも,日本の少子高齢化と人口減少も問題だとする二律背反のような授業をている方には,是非とも聞いてもらいたい講演であった。 最後は,神奈川県立三浦初声高校の金子幹夫先生と,渋谷教育学園幕張中学校・高等学校教諭の吉田真大先生から,全く異なる性格の高校での公民科教育のあり方についての発表があり,それをもとにパネルディスカッションが行われた。その際,公共の学習指導要領作成者でもある東洋大学文学部教授の栗原久先生から,作成者に経済学の専門家が全くいなかったとの発言があり,驚きを覚えた。 いずれにしろ県内の研修会では体験できない貴重な機会であった。 (県立湘南高等学校定時制 三橋 健彦) |